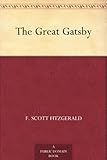「ペンは剣よりも強し!」って最近とんと耳にしなくなったが、あれはやはり義務教育のあたりで先生が口を酸っぱくして云い聞かせるものなのであって、大人同士の会話で使われないのは昔からなのだろうか。そもそも言論の力で暴力をねじふせることがかなった例などありはしまい。よくて言論が暴力を喚起し、これをもって別の暴力をはねのけたぐらいの話であろう。
政治学の教室ではかろうじて「ハードパワー」(軍事力)「ソフトパワー」(経済力、たまにちょっとした文化的発信力)の相互補完、機先なんてことが論じられていると思うのだが、一般に昨今の世は迫る剣の脅威に対していきおい「目には目を、歯には歯を」の論調であって、小学校の先生がこれを云うと教室は崩壊というか弱肉強食の世界になる。国際関係論ではこのモデルを「パワーポリティクス」といって、そうした考え方に立つ主義のことをリアリズムと呼び習わしている。
あろうことか「リアリズム」である。
なんかこの、粗暴な世界。力なくして自由を守れないのは真理にしても、それをわざわざ言葉にしなければならない時代の貧しさったらないよね、ほら柴田元幸が「リヴァイアサン」のあとがきに書いていたあれ、
「現実と理想との隔たりに人間の悲惨があり、現実から理想に向かおうとする意思に人間の栄光がある」
この決して実現しない理想に向けた逃走、その栄光こそがリアルだとどうしていえないの、などと他人事のようにため息をついていたら、おもいがけずこんなことを知らされた。
実は、リシュリューが言ったのは、 「権力のもとでは、ペンは剣よりも強い」 ということだったそうでそれが間違って伝えられてきたそうです。
つまりリシュリューは、 国家に反旗を翻し、反乱を企てる輩に対して、いつでも逮捕状や死刑執行命令にペンでサインが出来るんだぞと脅したのです。
「権力のもとでは、ペンは剣よりも強し」 - 練馬区大泉学園・「もんじゃ焼きお好み焼き わらべ」のつぶやき - Yahoo!ブログ
「わざわざ剣をもって切り結ぶには及ばん、あんなヤツ令状ひとつでほれ、逆賊よ」とこういうことだったそうで、このリシュリュー卿はそれこそパワーポリティクスの教科書であるキッシンジャーの「外交」に登場するヒーローの1人であるからにはさもありなんというか、逆に剣もペンも両方持ってる権力側の使う言葉だったんですねということでおあとがよろしい。
むかっ腹が立つとどうしても先に手が出てしまうガキ大将をいさめて「ペンは剣よりも強しって云うんやで!」と先生が云ってた姿を思い出すと皮肉な笑いをこらえられない。つわりだったのにノイローゼと保護者に説明されて学年の途中で休職に入った和久田先生、お元気だろうか。
* * * * *
いずれにせよこの誤りは正した方がいい。
あらゆる力のなかで暴力が最強であり、唯一抗えない力だということははっきりさせておかないと、文明が暴力を封じようというとき邪魔になる。
怒鳴るという行為が暴力であるという認識は日本には皆無といってよく、これで米国の空港で逮捕される日本のサラリーマンがでる。 流石に国際線だと日本人の悪しき行為に慣れている従業員が多いが、ファーストクラスで怒鳴って逮捕されかけたおっさんを知っている。(会社の威光で赦免されている。)
これがファーストクラスでアメリカへ行けるようになるまで偉くなるというのだから、とかくこの世は生きづらいというものだろう。
乱痴気ミュージカル映画「ムーラン・ルージュ」を撮ったバズ・ラーマンの「華麗なるギャツビー」はあらゆる予想を裏切って、良かった。
クライマックスはこうだ。
ニューヨークはダウンタウンのスイートルームで展開する一幕、若手のイケメン大富豪に妻を奪われそうになったトムがその素性を暴き立て、挑発に我を忘れたギャツビーがトムに向かって怒声を張り上げる。
生まれ育ちを恥じてたどった長い道のりの果てに名家の娘と結ばれるのにふさわしい階級(Class)と気品(Class)を手に入れたと思ったギャツビーの仮面が無情にもはがれ落ちる瞬間として描かれ、目の覚めるような効果をもたらしている。
これは怒鳴り声というのがSlapであり、暴力だからだということをあとになり、先のツイートで知った。
1920年代、待ち受ける大恐慌をいまだ知らず未曾有の好況にわきたつアメリカは世界の頂点に立つほんの手前であった。だが移民の国であり開拓者の国であるアメリカは、エネルギーに満ちあふれた輝きの奥底でヨーロッパに心をとらえられている。
名家、つまりはイギリスに起源をもち言葉遣いや暮らしぶりからしてそれを隠そうともしないロングアイランドの住民たちには決して追いつくことができないというのは、実はそれこそが新世界の民であるアメリカ国民の自由の源泉であるわけだが、デイジーに心を奪われたギャツビーは自分の運命に向き合うことができない。
アメリカの「存在しなかった過去」、自分とデイジーが結ばれるはずだった「存在しない過去」に向けて生き急ぐのがジェイ・ギャツビーという男だ。映画のラストシーンに向け、ギャツビーはあと一歩のところで望んだ世界から拒絶されて何者でもない誰かに戻らなければならない。そのシークエンスに選ばれた演出が彼の激昂であった。この描写は原作には存在しない。
服装も、言葉遣いも( "old sports, " )、クルマも家屋敷も、ヨットの趣味も政治家の友達も、盛大なパーティーが繰り返される数々の夜も、すべてを手に入れたギャツビーが唯一手に入れられなかったもの、それは「過去」であり、アメリカの過去に生きるデイジーという人だった。
伸ばしたその手が決してとどかないことをトムに指摘され、焦りに駆られたギャツビーは怒声をあげてしまい、それまでそこにあった彼への尊敬や信頼、親愛の情は一瞬で霧散する。その場にいあわせた「仲間」は彼以外、みなあちら側の人間だったからだ。
この世に暴力など存在しないと信じて生きる、無垢な世界の人々だったからだ。
戦争や貧困を知り、それを押し隠しながら生きるギャツビーの人間的な、きわめて人間的な存在とはそもそも遠くかけ離れた彼らは「もうひとつのアメリカ」であり、やがて岸を離れて霧のなかへ消えゆくアメリカだ。
ふたつの世界に生きる主人公だけがそれに気付いており、アメリカが引き裂かれて漂流し始める「ある晴れた朝」を悼む。やがて世界の大舞台に踊り出すのは果たして、理想を生きる古い方のアメリカではなく、理想を語るアメリカである。
スコット・フィッツジェラルドはここまでしか書いていない。
いままでのところ、アメリカの理想は暴力によってしか購われないというその栄光の道のりについては別の機会を待たなければならない。
とまれ、バズ・ラーマン版「華麗なるギャツビー」は大変な、ギャツビー愛にあふれた出来映えである。
なお原作の「The Great Gatsby」はKindle版を無料でダウンロードできる。
あまりにも有名な最後の1ページをぜひ味わっていただきたい。