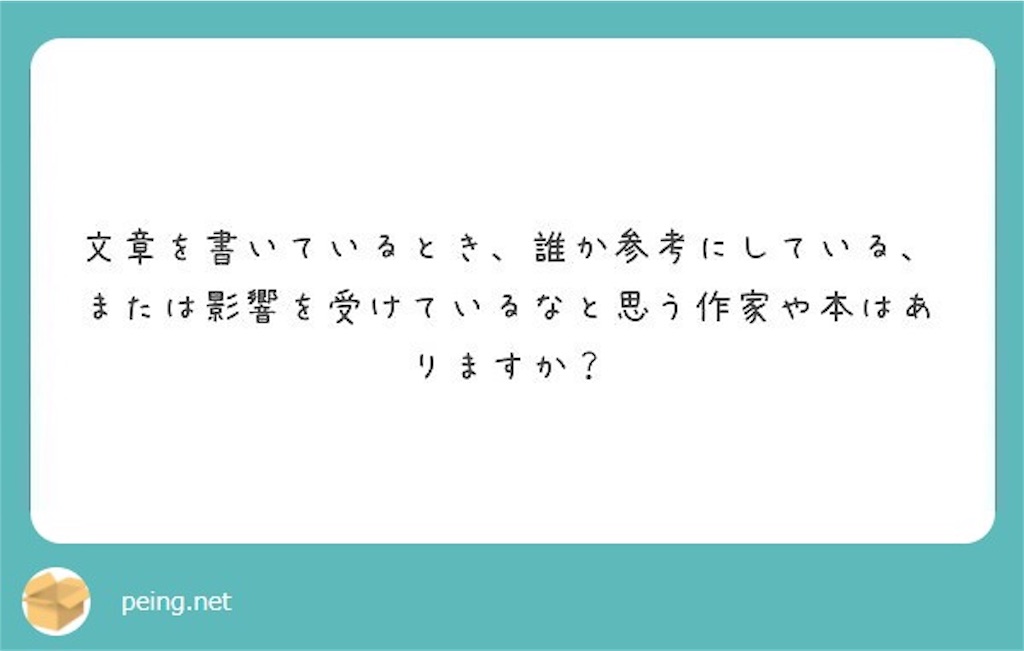アンコール・ワットを知ってるだろう。
私はアンコールワットを、その「樹海に侵食された遺跡」という誤ったイメージから「失われた伝説の都」だと思い込んでいた。
そこで彼の地を訪れた際には現地のガイドに何か鋭いことを云ってやろうと思い、
「こんな巨大なものが長いあいだ人目にも触れず、忘れ去られていたわけがないだろう!」と怒鳴ったら、
「いやジモトでは、みんなシッテタ」
と云われてクソ笑ったことがある。
誤解は小学校の図書室で借りた本にあった「アンコール・ワットを発見した探検家たち」の話に端を発しており、これは今なら不思議もない単なる「西洋による発見」に過ぎなかったのだと合点がいく。
もう少しいえば、そもそも樹海に侵食された神秘の遺跡という意味で「ラピュタ」のモデルになったとか「機動警察パトレイバー2 The Movie」の冒頭*1に登場する遺跡だとか云われているのは正確にはアンコール・ワットではなく、しばらく離れたところにあるタ・プローム遺跡だから、お出かけの際にはお間違えのないようご注意いただきたい*2。
もっとも私の場合、タ・プローム遺跡はとにかくそのガイドが
「『トゥームレイダー』の撮影でアンジェリーナ・ジョリーがきた」
と5,000兆回ぐらい繰り返したので、もうそういうイメージがついてしまい特に感慨がない。
「おまえさっきから『トゥームレイダー』『トゥームレイダー』ってうるさいけど『トゥームレイダー』なんかゴミだし、アンジェリーナ・ジョリーに興味ある日本人も全国に二十人ぐらいしかいないからな!」
と、云いたい気持ちを抑えていたら帰る時刻となった*3。
ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの夫妻はベトナムとカンボジアからそれぞれひとりずつ養子を迎えており、両国社会はこのカップルに対してひどく好意的だという印象だ。
ホーチミンシティには僕が知る限り「ブラピとアンジェリーナ・ジョリーがきた」と伝わるレストランが2軒あり、僕もお客さまをご案内する際には得々とそのエピソードを語るが、やはり日本人の反応はおしなべて弱い。
ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー、離婚成立へ。|ニュース(海外セレブ・ゴシップ)|VOGUE JAPAN
ところでアンジェリーナ・ジョリーの父親はジョン・ヴォイトで、「トゥームレイダー」では親子が共演していることになる。
そのジョン・ヴォイトのキャリアハイはおそらく「真夜中のカーボーイ(Midnight Cowboy)」(1969年)で、この映画は邦題が原題を圧倒的に凌駕している。
さらに余談を重ねるならば、米国による経済制裁が解除されるという歴式的なタイミングでベトナムを訪れた当時のビル・クリントン大統領*4が飯を食ったことを売りにしていたベンタン市場のPHO2000は一階をチェーンのカフェに奪われて空中店舗となったが、味がさらに落ちてもう行っていない。
ハノイでオバマ大統領が食ったブンチャ・ハノイはオバマとは無関係に永遠だ。
* * * * *
もう随分と長いあいだ、ブログも書かず、またSNS映えのしない生活を続けてきた。
インターネットではただ自分の痕跡が失われてしまわないよう、誰にでもできるようなポストをただ必死に繰り返すばかりだ。
しばらく前まではFacebookで見かけた記事をTwitterへポストし、バズってるツイートをFacebookでシェアすることによりコミュニティ間の情報格差を「いいね!」に替えており、マーケットでこれはクロスボーダー裁定と呼ばれるが私のやっていたのはまさに乞食の所業である。
あるいはFacebookにイヌやネコ、不細工なガキ、食いかけの飯、家から出た瞬間の空、そんな写真ばかりアップロードしているあなた方に「いいね!」するのはみんな、私のブログを読みにきてもらうための悪質な客引き行為にほかならず、私はそれらの写真自体にはほとんど興味がない。
正直に云えば、あなた方のポストは退屈だし、時にグロテスクだ。
それでも私は当ブログへのアクセスを伸ばすためなら敢えてそんなこともする。なぜならそれが右でも左でもなく愚かさへと、無知蒙昧の奈落へと急速に傾斜していく現代とこれからの歴史を向こうに回した私自身の闘争だからだ。
ソーシャル・ネットワークを通した、燃え盛るブログを掲げる闘争だ。
だからどんなに危険だといわれていても、私は届いた友達リクエストにはすべて応じているし、たとえそれがありえないレベルの巨乳など明らかなスパムアカウントだったとしても例外ではない*5。
差し支えなければこういいかえてみよう、つまり私は私なりに人類とこの社会を愛している。
最近、「資本主義の思想史」という本を読んで、私は自分が戦っている相手の名前を改めて知った。
中世、というのがそれだ。

資本主義の思想史: 市場をめぐる近代ヨーロッパ300年の知の系譜
- 作者: ジェリー・Z.ミュラー,Jerry Z. Muller,池田幸弘
- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社
- 発売日: 2018/01/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
中世はやはり暗黒だ。
まず知識が僧院の書庫に幽閉され、ひとびとの理性がふたたび無明の闇におかれたという意味で紛う方なく暗黒だ。そして宗教が、あるいは権力が宗教を用いてひとびとの精神を支配したという意味でさらに暗黒なのだ。
しかし、あるときそこへ活版印刷が現れる。グーテンベルクがやってしまう。
書庫が開かれ、書物から情報が引き剥がされてあまねくひとびとのもとへとコピーされていってしまう。漫画村状態になる。
次に疑念が生まれる。つまり理性が目覚める。
身分と土地に縛られ、分を守って生きていくのに理性は要らない。親のまねをして大人になり、そのまま同じ仕事を引き継いでやっていく。ザッツ・オールだ。規律と賞罰があればある種のネズミにだって同じことができるがネズミに理性があるとは誰もいわない。それは飼育であり隷属だ。
だが情報は違う。
情報というやつは全体として整合しない。あるいは全体をもたない。あるいは整合したふたつの情報はもはやひとつの情報だから、また他の情報とコンフリクトする。そこに議論が生まれる。考えるということが必要になる。「いや、さすがに?」*6という奴が出てくる。
インターネットを開いてみよう。すぐに反対する奴がいる。「いやそれは違うと思います」という奴が出てくる。これはバカだ。すぐわかる。違うのは当たり前だからだ。同じだとしたら、それはソースが同じなのであってまだ誰も何も考えていないだけの話だ。そうではない。「この違いはどこから来るのか?」「この違いはどこへ行き着くのか?」「この違いは実はどこかで整合するのではないか?そうしてやがてひとつの情報になるのではないか?」ということだけが議論なのだ。それが理性の働きなんだ。
「そんなのキリないじゃないですか」という奴がいるだろう。
キリがないんだよ。お前、中学校で習う数学が確立されるまでにどれだけ時間がかかってると思ってるんだ。進化論すらダーウィンから100年以上経ってまだ片付いてないんだよ。それが情報なんだ。知識なんだよ。常に理性によって疑われ、磨かれて消え去り、あるいは残るもの、それがあの暗黒の中世以降に人間が得たもののなかで唯一価値のあるものなんだ。石版に刻まれた戒律なんかお前には何も与えてくれないだろう、それはお前から自由を奪うためのものなんだから。
知識をもたないやつには疑念がない。これ以上はさすがに危険すぎていえない。だが中世が知識を隔離したのは目的からすれば正しいムーヴだ。中世の農奴にとって生きるために必要なこと以外に「知識」といえるものは聖書一冊分しかなかった。生きるために必要な知識を疑えば死んでしまう。聖書に書いてあることは読めないから疑いようがない。だから好色な聖職者の口から出る言葉がすべてだった。「イエスがこう云ったんだ!いいか?な、うん……」と云われればエッチなことをされてもそういうものだと思うしかなかったのだ。自分には聖書が読めないのだから。me tooかどうかも分からないのだ。他の人に話せば雷に打たれて即死だとかいわれるのだから。炎に焼かれて二目と見られぬ顔になるとか云って脅されるのだ。たぶん。
だからこのグーテンベルクというやつはかなりヤバい。「聖書?刷りましょう」とか云って刷ってしまう。自分が何をいっているかまったく分かっていない。そして大戦争が起きる。疲弊したヨーロッパでベルサイユがショートして爆発する。「やっていきましょう」といってナポレオン・ボナパルトが体制としての中世をガッとやってしまう。そのあとでイギリス人が「やっとるかー?」とかいいながらきてボナパルトを島流しにすると近代がやってくる。
だが中世は死んでいない。
その影を我々は今日も目にすることができる。
* * * * *
資本主義にはバグが存在する。
だがそれは構造的な問題ではなく修正パッチの配布が可能だ。
40歳になったらその開発に着手して「#うでパッチ」とか書いて引退するのが私の夢だったと云ってもいいが、うまくいかない。正直少し能力の限界も感じている。
一方で現代民主主義のハックがそれほど難しくないことはもはや明らかだといっていいだろう。こちらの方はだいぶん厄介だ。
民主政体というのはたとえば先進国だけをとっても国ごとに様々だから、そのどれもがそれなりに具合悪くなるというのは共通する環境に問題があるのだろうという見当はついていて、おそらくそれはインターネットの発達、つまり通信とストレージの爆発的な進化に対してヒューマン側、つまりインターフェースの進歩が追いついていないことではないかと思う。
この解決に時間がかかるのはもちろんのことだが、政治社会というのは「偉い奴が自分に有利なルールを決める」という性質上、どうしても強いモメンタムを生じるようになるから、いちどおかしくなったものがおかしくなるところまでおかしくなって、それから少しずつ本来のかたちへ戻ってくるまでの往復にはいまからだいたい500年ぐらいかかるのではないかというのが私の推測だ。
この500年を、私は人類史上第二の中世と呼ぶことにしている。
これから無明の世界にのまれようとする人類に贈る言葉はない。
だが500年後、ふたたび目覚めた理性の灯りで世界を照らし始める人類のために、私は本当の知識を、情報をできる限り遺したいと願う。
いろいろ考えたが、できることはふたつある。
それはちょうど、アイザック・アシモフの「ファウンデーション」*7と同じ数だ。
気を持たせるようなことを云ってしまったが、それは戦術だ。実はこのブログ自体はそのふたつに入っていない。このブログはいまから続く長い長い戦いの、いわばお通しに過ぎない。
無理に食ってくれとはいわない。だが勘定はいただこう。
そこにあるリンクを押せばいいのは分かっていると思う。
*1:「東南アジア某国」。
*2:ご存じない方のために付け加えると、アンコール・ワットは同じような遺跡が霞ヶ関みたいに大小取り混ぜて多数点在している「アンコール遺跡群」の一部なのだ。
*3:だだしこのガイドは日本語に堪能で人柄もよく、ご要望があれば名前をお知らせしたいと思う。あなたがその二十人の一人ならば必ずや楽しんでいただけるだろう。
*4:いまのところビル以外に大統領になったクリントンはいない。
*5:当然これは誇張であって、「共通の友達」がいる場合には承認しないことがある。
https://twitter.com/umesurebot/status/1000398090371678209
*7:20世紀の巨匠アイザック・アシモフが著したSF大作「銀河帝国の興亡」では、銀河帝国の滅亡を見通した心理歴史学者のハリ・セルダンが来たるべき復興の礎となるべく銀河の辺境にふたつの「ファウンデーション」と呼ばれる社会を用意する。